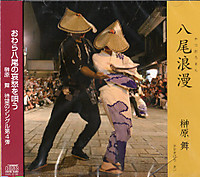島地勝彦さん「乗り移り人生相談」が単行本化、記念座談会。サロン・ド・シマジにて。11月に発売の単行本に収録される予定です。

左から一橋大学准教授の小岩信治さん、外資系IT企業に携わる森正貴資さん、「ミツハシ」こと担当編集者の三橋英之さん、中野、そして島地さんです。小岩さん、森正さんは、とても品のいい熱狂的なシマジ教信者。行動だけ聞くとかなり大胆な攻め系なのですが、人当りや言葉がとても丁寧で穏やか。ファンとしてじかあたりした森正さんは、なんとシマジさんとスコットランドに一緒に旅行するまでの仲に。やはり作家のレベルと読者のレベルは引き合うのでしょうか。「乗り移り」のコメント欄の読者の反応もレベルが高いことが話題になりました。
それにしても、シングルモルトがすすめばすすむほど男性の皆さんのお話が格調高くなっていくというのは(笑)。
じかあたりと運とご縁。一言付け加える「感想」。ほんのささいなことが仕事の質を上げ、縁を結び、人生を面白くしていくの図、まのあたりに。
salon de shimaji オリジナルラベルがかっこよすぎる。
先日、ご紹介した’I am a Dandy’。本の出版を祝って、サヴィルロウ一番地のギーヴズ&ホークス本店でパーティーが開かれたそうなのですが。
出席した方々のユニークな個性にしばし釘づけ。(上のリンクから出席者のファッションが見られます)
クラシカルダンディが好きな人は眉をひそめるかと思いますが、今はまあ、「トレンド」としてのダンディズムの表現は、こんなことになってる(のもアリ)なのですね。
こういうの、なんて形容するのかと思って関連ブログなどチェックしていたら、swellegantという表現にいきあたりました。swell+elegantね。日本語でどう訳せるんだろう? 当面の課題です。
スーツの季節、そろそろ到来ですね(シーズンレスな服ではありますが、クールビズが終わり、秋冬向けウール素材でのスーツの季節が本格的に始まるという意味で)。
先日出席した駐日大使歓迎ディナーのドレスコードは、「ビジネススーツ」でした。会社帰りの方にもご配慮して、とのこと。
スーツを着るのが当然という世界がある一方、就活したくてもスーツ一式を買えない、買えないから面接に行けない……という悲しいスパイラルもある。安いスーツがあるといっても、靴、バッグ、シャツ、時計などなどの小物をひととおり合わせなくてはならず、その小物にこそその人の背景が表れてしまうというのがスーツの恐ろしいところでもあるし。「若年無業者の4人に1人がスーツを持っていない」という記事。↓
http://blogos.com/outline/70057/
なんでここまでスーツが常識なのか。
イギリス人が19世紀に植民地政策とともに英語&ジェントルマン理念とセットで世界に普及させ、それが定着して、いつのまにかルールになってしまったらそれが勝ち、って考えてみたら無茶苦茶なことですね。これほど周囲から「監視」され、バリエーションが許されない服というのも珍しい。成文法なんてどこにもないのに、なにが「正しい」のか、大真面目に議論され続ける。スーツを着て働き、社交しなくてはならない男性のみなさん、息苦しくないですか?
「たかが服、どうでもいいことだから、慣習にしたがっとけばそれがラク。ほかにもっと真剣に考えなくてはならないことがある。それになんだかんだといってスーツは男をかっこよく見せてくれるし」。そんなところでしょうか。
「正しさ」の根拠なんて、ほんと、いいかげんで、きわめて人間くさいものです。多くの場合、「歴史」のなか、「起源」をたどると、その「正しさ」の根拠らしきものが見えてきます。ふりかざされる「正しさ」にどのように対処するか、それがスーツの着こなしにもあらわれてきますね。ゲームのルールを厳守するのか、ルールをもてあそぶのか、ルールからはずれてしまうのか。その姿勢にこそ、教養やら性格やら社会的な立場やら各種余裕の有無やらエゴやら、とにかくいろんなその人のことが見えてきます。
その「起源」にしても、いろんな考え方があるのは当然。ひとつの事象の見方は、人間の数だけあります。起源ですら絶対ではなく、あくまで、ひとつの解釈。そこまで理解して、はじめて、あなたなりの「正しさ」とのつきあい方が決まる。
以前に告知しましたが、あらためて。10月に、明治大学リバティアカデミーにて、はじめて社会人向けスーツ公開講座を担当します。私の<歴史編>と「丸井」のバイヤーさんによる<実践編>からなる連携講座です(セットにはなっていますが、どちらか片方だけ受講していただくということでもかまいません)。スーツについて多角的に学びたい方、その入門編としていかがでしょうか。このマイナーなテーマにしては申し込み順調につき(ありがとうございました)、来春も開講が決まりました。とりあえず、10月の講座はまだ少し残席あるそうです。お申し込みはこちらから↓。
https://academy.meiji.jp/course/detail/1369/
電子書籍「スーツの文化史」(→)も参考書としてどうぞよろしく。
[E:maple]だいぶ時間がたってしまったが、8月29日付の朝日新聞、ファッション欄、「欧州ブランド、日本人とコラボ」。今シーズンに見られる第三次ジャポニスムの流れを紹介。以下、備忘録として。数式メモで御免。
・ロエベ×渡辺淳弥 「ロエベ・アンド・ジュンヤワタナベ・コムデギャルソン」。
ロエベの高級革×淳弥のデニム=贅沢さ×ストリート感覚=上品さとロックの反骨精神。
・モンクレール×相澤陽介=モンクレールW
ダウン×ジャガートなどカジュアル異素材。ひじやひざ部分が曲げやすいようにステッチを施すなど、東京ブランドらしい「かゆい所に手が届くような仕立て」。
・プチバトー×メゾン・キツネ(黒木理也+ジルダ・ロアエック)
○日本独自の伝統的な美意識=非対称的で平面的な構成、異なる要素の大胆なミックス感覚、素材への深い配慮
>自然の微妙な変化を愛で、自らも自然の一部として共に生きようとする日本人の姿勢
○第三次ジャポニスムは、和魂洋才の新しいカジュアル感覚。
[E:maple]こちらも。WWDジャパン7月15日号。vol.1756。
「鎌倉シャツ」がNYマディソンアヴェニューに進出、黒字の見通し。200ドル前後の同品質のものを79ドルで提供するというのは、驚きをもって歓迎される。ただ、試行錯誤も多く、その一つが胸ポケット。
「日本ではペンや定期券を入れる人が多い。貞末会長も欧米の正統派のドレスシャツにポケットがないことは承知していたが、日本では胸ポケットのないシャツは売れないため、そのまま残していた。だが現地では総スカン。『世界で活躍するビジネスマンのためのシャツを作ってきたのに、海外で「鎌倉シャツ」を馬鹿にされたのでは話にならない』と社内の反対を押し切り、国内の商品を含めて胸ポケットの撤退を決めた」
「またブルー系を大幅に増やし、ダブルカフスのシャツを拡充したのも、顧客の意見に従ったMD変更」
シャツに胸ポケットは異端です。でも日本人にとっては便利なんですけどね…。「正しさ」と「利便性」のせめぎあい。メンズビジネススーツのシステムにおいては、「正しさ」が勝利するというエピソード。
[E:maple]同号、目次ページのChat Chat!
ミュージシャンの久保田利伸がポール・スチュアートのCMに出るに際して。
「ノリを追求した落ち着きのない音楽をやっている自分が、ビシッとしたスーツを着るミスマッチがオシャレ。僕だけでなく世界中のファンキーミュージックピープルが、ビシッとしたスーツやネクタイでステージに立つことが増えている。良いスーツを着るとスイッチが入り、ノリの激しい音楽を歌うのが気持ちいい」
スーツにはこんな効用もあり。
同じ人間界の話とは思えないほどかけ離れた世界の話だったが、面白すぎて一気読み。超富裕層のお話。
ロバート・フランク著「ザ・ニューリッチ」。リッチスタン(富裕層の国)のお話。2007年の本だから、今は昔…な話も多々あろうかと思うのだが。それでも、アメリカの新富裕層の実態が赤裸々に描かれており、興味がつきなかった。執事、起業、慈善、パーティー、ヨット、ジェット機、スパ、城、屋敷内ゴルフコース、デスティネーション・クラブ、美術品…。
以下、とくに面白いと思った引用&概要など、備忘録。
・現在の執事は、「ハウスホールド・マネージャー」
・富裕層が安心できる金額はほぼ常に、現在の純資産額あるいは所得の約二倍。
・有閑階級は一変しつつある。暇なお金持ちに代わって、仕事中毒の富裕層が登場している。
・富は人間の最低の部分も、最良の部分も引き出す。つまり、富は人間性を誇張するのだ。「金は自白剤のようなもので、人間の本質を引き出してしまう。だから、嫌なやつは金をもつとますます嫌なやつになる」
・映画みたいだ、と感じたのが、社交界の頂点をめざすファイマン氏のエピソード。赤十字ダンスパーティーに100万ドルという史上最高の寄付をすることで、パ―ティー実行委員になる。いわば、社交界を金で買おうとする。これが守旧派の大ひんしゅくをかう。あれこれの小競り合いがあって、ファイマンは文字通り転落(舞台の上から)。厚かましい野心家の失態として大いにオールドマネーを喜ばせたというエピソード。
・新旧の確執は古くから。古代ギリシアでは、香辛料や香水、亜麻糸といった贅沢品の輸出入で財を成した貿易商がニューリッチとして台頭したが、彼らと地主階級とのあいだには繰り返し争いが起きている。
・古代ギリシアのニューリッチは、オールドリッチに打ち勝とうとする一方で、彼らの仲間として受け入れられることを必死に求めていた、とギリシアの歴史学者チェスター・スターは述べる。「富と地位を手に入れたカコイ(ニューリッチ)は、社交面で貴族を真似ようとした。こうした社交上の意思表明は、たとえそれが貴族への賞賛であったとしても、おそらく貴族の目から見れば、この上なく苛立たしいものだっただろう」
・オールドリッチとニューリッチの確執は、1800年代後半から1900年代前半にかけて、さらに激化する。新世界アメリカの産業王や鉄道王たちが、ヨーロッパの地主貴族階級に挑戦しはじめた時代。
・金メッキ時代のアメリカの富豪たちも、貴族階級より裕福ではあるものの、ヨーロッパの王室に認められ、賞賛されることを常に求めていた。
・今日のリッチスタン人も、上流階級の門戸を突き破ろうとしている。それがオールドリッチとニューリッチの新たな確執を生んでいる。100年以上前の金メッキ時代と同様、いまのアメリカでも、ニューリッチが富裕層コミュニティに大量参入し、血筋や家柄ではなく、金に基づく社会的ヒエラルキーを築こうとしている。
・リッチスタン人にとって、名士録に名前が載ることなどもはや当然のことだ。彼らが競って登場したがるのは、「ハンプトンズ」「アスペン・ピーク」「ガルフショア・ライフ」といった新種の社交雑誌。
・今日の即席起業家出自はさまざまで、明確な「支配階級」もなければ、ニューリッチ全体に共通する価値観もない。旧富裕層は、慎みや伝統、公共への奉仕、慈善、洗練された余暇活動を誇りとしたが、リッチスタン人が誇りとしているのは、ミドルクラスの倫理観と、自力で築いた資産、そして高額消費。
・「ニューリッチの夢はこうだ。ある日、町の名門一族の主が名刺ファイルを繰って、電話をかけてくる。そして、こう言う。『君のお金が必要なんだ』。そこで金を出し、仲間に入れてもらうというわけさ」。
・パームビーチの決まりごと。一度着たドレスを別のパーティーに着ていくのは厳禁。目立つブレスレットと目立つイヤリングを両方つけるのはいいが、目立つネックレスまで一緒につけるのは、やりすぎ。
・慈善パーティーの実行委員長になって賞賛されるためには、金持ちの友人を総動員し、大金を寄付してもらう必要がある。しかも、集めたのと同じ金額を自分も寄付しなければならない。もちつもたれつのおかげで、金さえ積めば慈善家としてパームビーチ社交界での地位を築けるようになった。しかも、寄付はすべて課税控除される。
・ベントレーは、15万ドルとやや手頃だ。ベントレーによると、需要が非常に高いので通常の広告を打つ必要はまったくないという。「この車を買える人は、向こうからわれわれを見つけてくれます」
・美術品は壁を飾るだけでなく投資にもなると、ニューリッチは信じている。資産マネージャーやファイナンシャル・アドバイザー、美術商、ギャラリー、それにオークション会社が結託して、美術品は蓄財の手段だと宣伝している。チャック・クローズの肖像画は、ただの絵ではなく「リスク相関のない資産」であり、美術品は居間のバランスだけでなくポートフォリオのバランスも整えてくれるのだ。
・美術商は、美術品を金融商品に変えることで、美術品市場のリッチスタン人にとっての魅力をぐっと高めた。
・支出のトリクルダウンは、野心のトリクルダウンを伴う。これほど多くの富裕層が財力を誇示するのを見て、ミドルクラスやアッパーミドルクラスでさえも急に相対的な貧しさを感じ、負けじと身の丈以上の支出をしはじめる。
こういう側面を知っておかないとラグジュアリー業界の見え方が片手落ちになる。といっても本に書かれていることすら、ごく一部の話だと思うが。
今日、届いた本の中から。

これは……ちょっと衝撃でした。Nathaniel Adams, Rose Callahan, ‘ I am Dandy; The Return of the Elegant Gentleman ‘, Gestalten.
ハードカバーを開くとショッキングピンクの世界(文字通りのイミです)。今どきのダンディ約60人のグラビアなわけですが。それぞれに、凝りに凝った宇宙人のような装い。ぞわっとくる。必ずしも「魅力的」ではない。けれど、目をひきつけずにはおかない超個性派ぞろい。
序文にグレン・オブライエンはこんなタイトルをつけている。「ダンディは危機にある世界に希望をもたらす」。
反発と興味をともにかきたてるという意味では、まちがいなく、今日的ダンディ。ふつうの生活を送っている人の目には、ブキミに見えます。まさしくそこが彼らの狙い。
この本については、あらためて、ダンディズム連載などの記事で紹介したいと思います。
ワードスパイの新語から、最近、知ったことば。以下、関連のランダムなつぶやき。
・Frenemy (>friend + enemy) フレネミー。初出は1953年。前からあるんですね。表向きは「フレンド」のふりをしているが、実は裏では足を引っ張る敵のこと。
おそろしい。フレネミーが10人いるくらいだったら、一人でいたほうがはるかに幸せ。
現実がそれだからこそひとしお、なのかもしれないが、フレネミーぞろぞろの「ゴシップガール」の世界が面白すぎる。すでにシーズン5の「これでもか」の世界に完全に染め上げられ中。毎回のビターな結末と教訓が中毒になる。
このシーズンで登場するダイアナ役のエリザベス・ハーレーのビッチぶりもかっこいい。投資家という設定みたいだが、なぜか職場にいつもボディコン露出過多のセクシードレス。イギリスなまりの発音にカンロクありすぎ。
ダイアナ・ペイン役のハーレー。毎日この手の姿でオフィスに。ネイト役のチャンス・クロフォードもEpitome of ideal woman と称賛。彼女は私とほぼ同年代。カテゴリーが違う方に希望を見てもしょうがないが(笑)。
・Dioworsify (>diversify + worse) たとえばリスクを分散させようとしてますます悪化させること。断ることができずになんでもひきうけ、結果、多様化して状況が悪化しているというのは私のことですね(T_T)
・shampaign (>sham + campaign ) インチキで不誠実なキャンペーン。とりわけ政治的なキャンペーンに対して。2020東京オリンピック決定に対しては、もちろん祝意を表するものではあるけれど、直前の首相のスピーチに対して感じたのが、「シャムペーン」ではなかったかということ。福島の汚染水の状況が完璧にコントロールされていると世界に対して言明できるって……。
ビターサイド、グレイサイド、ダークサイド、生きていれば必ずくっついてくる。あれやこれやの状況をすべて併せのんで少しでも希望の見える方向へ進まなくてはね。
博報堂が出している「広告」。レイアウトがひどく読みづらいのですが(スミマセン)、読みやすいところからつまみ食いする形で前後読んでいくと、示唆的なメッセージに行き当たることが多いのですね。
今号でいちばん興味深かったのが、IDEOチーフクリエイティブオフィサーのポール・ベネットさんのインタビュー「物を売るための神話から、TRUTHのあるストーリーテリングへ」。以下、ほとんど自分自身のための備忘録です。書きっぱなし御寛恕。
TRUTHとIMPACT。
大事なのはわかるが、では、TRUTHとはなにか。
「人々がどう生活するかをとにかく観察して、人を理解しようとすること。人は生活のどういう局面で、なにを必要とするのか、何を欲するのか、どのようにコミュニケーションするのか。
僕たちは『出どころのない、物を売るためだけの神話』をこしらえることには一切興味がなくて、すべてのストーリーにはそういう人の生活にやどるTRUTHがあるかどうか」
TRUTHの部分が、いかなる立場であれ、重要、と。
「どんな状況に立たされようと、クライアントに対しても、社内に対しても、人が望むものはこれです、と胸を張って言えるものがあるかどうかが、これからのクリエイターのすべてを決めると思う」。
だから、そんなデザインは、政治ともかかわってくる。
「デザインのために、生活するひとびとを見つめる。ひとびとが仕事する様子をじっくり見つめる。学校に通う姿をじっくり見つめる。親子の関係を見つめる。そういうプロセスの中から、生活の根底にある本質を見つめて、生活をよくするソリューションを出すんです、と。
すると、一人の議員が急に叫んだ、それがまさに政治家がすべきことじゃないか!と」
で。IMPACTは、
「人の心に梃子が当たっていなければならない。構造にも、使用方法にも、新しい発見がなければならない」
表現は、シンプルに。
「要素が昇華しきれてない、ふたこぶらくだみたいなのは、持ってこないでね」
IDEOをIDEOたらしめているのは、スタンフォード大学内にあるd.school.
「マーケティングによる最適解を出すという問題設計よりも、デザインが持つ人々の心理、生活、人生、文化、エコシステムを貫通できる問題設計の方が、より本質的で創造的ソリューションを社会に提供できる」
「良い会社はより大学みたいに、良い大学はより会社のように、急速になっている」。
「コラボレーションとはすなわち越境であり、いろいろなバックグラウンドのひとがぶらぶらしている『必要』がある」
鈴木光司さんの長編『エッジ』が、アメリカのシャーリー・ジャクスン賞を受賞。「変人」が40人ほど集って祝賀会がおこなわれました。神宮前の「レストラン・アイ」にて。
メニューも、アミューズからして「白い粉灰、黒い灰チュールに包まれ 塩で『エッジ』を利かせたトリュフグラス」など、祝賀の趣き。
アメリカで売るために戦略を練った、という鈴木さんのお話が興味深かった。『リング』は世界中で売れたのに、アメリカではさほど売れなかった。おそらく、日本のローカルな土地で始まりローカルな土地で終わる話だからだろう、と考えた鈴木さんは、『エッジ』の舞台をアメリカにもってきた。アメリカの砂漠に始まり、アメリカで終わる話にした。アメリカ人は、案外、知っている土地の話だと読みたがる単純なところがある。その読みが当たった、と。
日本の本が世界で「売れる」ための戦略はまだまだありそう。
貞子さんもお祝いの席にいらっしゃいました! あらためて、受賞おめでとうございます。
尊敬するコラムニスト、闘病中の神足裕司さんが、拙著、「スーツの神話」について、こんなにも素敵なレビューを寄せてくださっていました。月曜日に放送されたTBSラジオだそうです。
神足さんの文は、つぎのように結ばれていました。
「そして後に出合った『スーツの神話』を読んで、
スーツの威力は本当だったと確信する。
いまでも「スーツの神話」は僕のお守り的な本。
ボロボロになってしまっても、
それを直し直し着るのがスーツを愛している人の着方なのだそうだ。
それを実践しよう。
『スーツの神話』も持ち歩いてるからスーツ同様ボロボロなのです。」
泣けました…。これほどうれしい言葉があるでしょうか。私も、このお言葉を心の中に持ち歩き、お守りにしたいと思います。
神足さま、ありがとうございます。一日も早い全快を、心から祈っています。
レビューのことを教えてくれた友にも感謝します。
☆文春新書のこの本は絶版中ですが、Kindle版で「スーツの文化史」として電子書籍になっています。→の本の写真をクリックしていただくと、amazonに飛びます。宣伝御寛恕。