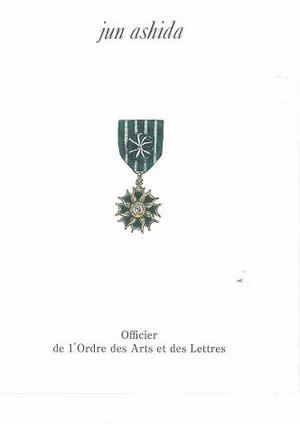堀井憲一郎『江戸の気分』(講談社現代新書)読み終える。落語を通して、江戸のリアルな気分のなかにひたって、江戸の庶民になった感覚を想像してみよう、という趣旨の本。
肩肘はった分析を試みる評論家の態度じゃないのが、いい。ゆるい「江戸内部の人」感覚でおしゃべりをするような感じで書かれているが、ゆるさを正しく表現するのも、筆力が要ることである。以下、なかば衝撃とともに知ったこと(の一部)。
・医者は患者を治さない―「落語では『病い』を『引き受ける』という。(中略)病いは自分の内にあると考えているわけで、そのへんは、江戸の人の方が長けている。(中略)近代人は、病気をすべて『外のもの』として捉えるのがいけないやね。外のものがやってきて、自分のからだを侵食していくから、これをまた外に排除してくれ、医者だったら排除できるだろう、と考えているのは、近代人の異常性だとおもう。(中略)よくわからない身体の不都合は、『引き受け』ないとしかたがないのだ」
・武士とは武装軍人である―「武士はそう簡単に刀を抜けない。抜いたら最後、相手を倒さねばならず、いろいろと面倒である。(中略)となると、乱暴な町人側から見れば、武士にいくら悪口雑言を浴びせても、相手が抜かなかったらセーフ、ということになる」「武器をいつも携帯している軍人である武士がそこにいれば、身分の差がありありとわかる。武装軍人は、身体的に別存在である。関わりたくない。まったく別のエリアで生きているし、別のエリアで生きていたいとふつうにおもう。身分差とはそういうものである。頭でわかるものではない。身分の差はカラダでわかる。見た目でわかる」
・なぜ花見をやるのか―「冬が終わった確認のためである。(中略)飲んで眠ってしまっても凍死しない季節の到来、それが桜の開花なのである」
・蚊帳は結界―「蚊が多すぎて、少々殺したところで、事態が変わらない。(中略)殲滅するという無駄なことに労力をかけるよりは、自分たちの身の回りに蚊を近寄らせなければいい、という考えです。自らの非力を知って、自然の中で被害を小さくする方法を考えるってことですね」
・手厳しい長屋―「三月裏は、家の形が菱餅みたいにひしゃげている裏長屋。八月裏は年がら年中、裸で暮らしている裏長屋。長屋ぜんたいで釜が一つしかない釜長屋。長屋四十軒のうち三十八軒は冬の寒いおりに戸を叩き割って燃やしてしまっているのが戸なし長屋」「ついこのあいだまでは、わが邦には、本物の貧乏がそこかしこにあった。誰もが、いくつかの角を曲がると、死と貧しさを一緒に抱えてるエリアがあることを知っていた」「落語を聞いていると、おそろしく貧しい人たちも、バイタリティに溢れて生きていることがわかる」
・無尽―「十人で集まり、三万円ずつ出す。三十万円集まる。それを一人がもらう。その会合を十回続ける。(中略)あまり負担をかけずに、共同体内でまとまったお金を用意するためのシステムだった」
・金がなくても生きていける―「それを昭和の後半から末期にかけて、みんなで懸命に押し潰していった。(中略)社会全体が『金』でものごとを測ると決めたのだから、社会の端まで徹底的にそれで染めていったばかりである。ひとつ価値を社会の隅々まで広めないと気が済まないのは、うちの国の特徴であり、病気であり、また強みでもある」
・「顔」がお金の代わり―「同じところに住み続けているのが信用である。逃げない、ということだ。(中略)だから身の回りにあるもので生活する。豆腐は町内で買う。(中略)いま流行りの『お取り寄せ』というのは、つまり地域社会の破壊ですね。我欲で小さいコミュニティをどんどん潰していきます。お取り寄せの多くは、その土地に関する体験も経験もないまま、情報によって取り寄せて消費するという脳内先行社会によって支えられている」
・死なないまじないとしての食事―「朝は、あたたかいご飯と漬物。昼は、あたかいご飯と漬物におかず一品。番は、冷や飯に、漬物。これが日常食である。落語のなかで、夜によく茶漬けを食べてるシーンがあるのだが、それは夜のご飯が冷や飯だからだ」「食物を、カラダにいいという物語性の中で語ってくれなくていいです。死なないまじないの限度が知りたい」
東海道ラインが機能しなくなっても、東京から大阪まで歩くことを想像できる、という堀井さんの落語的感覚が描きだす江戸ワールドにひたっていると、ほどよい塩梅に力が抜けてくる。「最低限、死なない限度」を淡々と保つ心の持ち方のヒントを教わったような読後感。